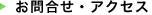ニュース
ニュース
|
2023年7月11日 |
近藤剛弘 教授(筑波大学数理物質系 エネルギー物質科学研究センター(TREMS))が、新しい電極触媒材料となる可能性のある物質として、埋蔵資源量が豊富なホウ素と硫黄が1:1の組成比で構成される菱面体硫化ホウ素(r-BS)の合成を報告してきました。本研究では、r-BSをシート状の炭素であるグラフェンナノプレート(GNP)と複合化した、r-BS+Gの合成に成功しました。このr-BS+Gをアルカリ水溶液中での水電解の電極触媒材料として用いたところ、酸素発生反応に対して高い触媒活性が得られました。r-BS+Gの触媒活性をさらに向上させることで、実用的なグリーン水素製造装置への応用が期待されます。 【業績】典型元素を利用した高活性アルカリ水電解触媒を開発。PDFはこちらです。 https://www.tsukuba.ac.jp/journal/technology-materials/20230711140000.html |
|
2023年6月1日 |
丸本一弘 教授(筑波大学数理物質系物質工学域 エネルギー物質科学研究センター(TREMS)) 発光電気化学セル(LEC)は、有機発光ダイオード(有機EL)と比べて構造が簡単で柔軟性にも富むことから、印刷技術を活用するなど低コストでの製造が可能です。また、有機ELより低い電圧で駆動できることなども利点で、次世代の省エネ発光素子として注目されています。 発光電気化学セルの動作機構について、これまでにない分子レベルの情報を提供することが可能となりました。その情報を基にすることで、低コストでより環境負荷の少ない発光素子の製品開発が効率良く進むことが期待されます。 【業績】有機ELより低コストな発光電気化学セルの動作メカニズムを解明 PDFはこちらです。 【日本語】https://www.tsukuba.ac.jp/journal/technology-materials/20230602180000.html 【英語】https://www.tsukuba.ac.jp/en/research-news/20230602180000.html |
|
2023年3月26日 |
マテリアル分子設計部門のPV 字幕なし https://youtu.be/x_rGEaVyYqQ 字幕有り https://youtu.be/8n2m-_9vyZU |
|
2023年2月11日 |
近藤剛弘 准教授(筑波大学数理物質系 エネルギー物質科学研究センター(TREMS))が、日本ホウ素・ホウ化物研究会の学術賞を受賞しました。 賞状はこちらです。 |
|
2022年8月5日 |
山本洋平 教授、山岸洋 助教(筑波大学数理物質系物質工学域 エネルギー物質科学研究センター(TREMS))らは、お椀型多面体マイクロ単結晶の均一かつ精密な成長制御に成功しました。 本研究結果は、分子の自己組織化により凹多面体マイクロ骸晶の形成を基板上で均一かつ精密に制御した先駆的な例であり、特に有機マイクロフォトニクス応用に向けた汎用性の高い有機マイクロ結晶形成戦略を提供します。 【業績】お椀型多面体マイクロ単結晶の均一かつ精密な成長制御に成功 【日本語】https://www.tsukuba.ac.jp/journal/technology-materials/20220805030000.html 【English】https://www.tsukuba.ac.jp/en/research-news/20220805030000.html |
|
2022年7月1日 |
武安光太郎 助教、近藤剛弘 准教授(筑波大学数理物質系物質工学域 エネルギー物質科学研究センター(TREMS)、ゼロCO2エミッション機能性材料研究開発センター)らは、大阪大学、九州大学との共同で、CO2水素化によるメタノール合成の反応過程を解明することに成功しました。今後、本研究結果に基づいて、フォーメート(HCOO)からジオキシメチレン(H2COO)への水素化過程を加速する触媒や反応システムを構築することで、CO2の水素化によるメタノール合成を低温化し、転換効率を高めることを目指します。 【業績】CO2水素化によるメタノール合成の反応過程を解明 【日本語】https://www.tsukuba.ac.jp/journal/technology-materials/20220701140000.html 【English】https://www.tsukuba.ac.jp/en/research-news/20220701140000.html |
|
2022年6月07日 |
西堀英治 教授(筑波大学数理物質系 エネルギー物質科学研究センター(TREMS))らの国際共同研究グループは、X線自由電子レーザー(XFEL)施設「SACLA」を用いて、X線を照射された原子はしばらくの間ほぼ停止していることを明らかにしました。本研究成果は、放射線損傷の影響がない精密X線構造解析を実現するための第一歩となるものです。 【業績】X線レーザーを照射された原子は遅れて動き始める~放射線損傷のない精密X線構造解析の可能性を証明~ 【日本語】https://www.tsukuba.ac.jp/journal/technology-materials/20220607140000.html |
|
2022年6月02日 |
羽田真毅 准教授(筑波大学数理物質系 エネルギー物質科学研究センター(TREMS))らは、光励起で起きる10兆分の1秒(100フェムト秒)以下の構造変化を観測するテーブルトップサイズ電子線回折装置を世界で初めて開発した。本装置では、従来よりも加速電圧を抑えた(10万ボルト)電子線を用いているため、試料損傷もほとんどなく、無機物質から有機物質まで広がる光エネルギー変換材料や光メモリー、トポロジカル材料など幅広い材料開拓への貢献が期待されます。 【業績】10兆分の1秒以下のコマ撮りが可能な電子線分子動画撮影装置の開発に成功~光が駆動する20兆分の1秒の結晶変化を観測~ 【日本語】https://www.tsukuba.ac.jp/journal/technology-materials/20220602140000.html |
|
2022年5月21日 |
近藤剛弘 准教授(筑波大学数理物質系 エネルギー物質科学研究センター(TREMS))が、2022年日本表面真空学会総会後の表彰式で、フェロー称号を授与されました。 【業績】新規ホウ素含有二次元物質の生成と機能の開拓 https://www.jvss.jp/jpn/news/detail.php?eid=00136 https://www.jvss.jp/jpn/introduction/fellow_jvss.php |
|
2022年4月20日 |
丸本一弘 准教授(筑波大学数理物質系 エネルギー物質科学研究センター(TREMS))は、電子スピン共鳴を活用し、従来の手法では難しかった三元系高分子太陽電池の安定性向上メカニズムを分子レベルで解明することに成功しました。独自に開発した太陽電池の構造を活用し、電子スピン共鳴と太陽電池の性能を同時に計測する、世界初の測定手法を用いた成果です。本手法で得られた分子レベルの情報を基にすることで、低コスト、高効率かつ長寿命で、環境にも優しい太陽電池の製品開発が効率よく進むことが期待されます。 【業績】三元系高分子太陽電池の安定性向上メカニズムを解明 ~塗布型で低コストの製品開発に貢献~ 【日本語】https://www.tsukuba.ac.jp/journal/technology-materials/20220420180000.html 【English】https://www.tsukuba.ac.jp/en/research-news/20220420180000.html |
|
2022年4月8日 |
中村貴志 助教(筑波大学数理物質系 エネルギー物質科学研究センター(TREMS))が、科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞しました。 【業績】機能性ユニットを精密配置した大環状分子に関する研究 https://program.chem.tsukuba.ac.jp/2022/04/08/1118/ https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00989.html |
|
2021年11月12日 |
近藤剛弘准教授ら(筑波大学数理物質系エネルギー物質科学センター(TREMS))は、これまでに理論的に優れた熱電特性や水素吸蔵特性を示すことが予想されていた硫化ホウ素シートを実際に生成することに成功しました。シートを重ねる層数の違いでバンドギャップが変化する半導体であることがわかったため今後、電子デバイスの半導体部品としての利用や、光触媒としての応用、光に反応するセンサー材料などの幅広い分野への展開も期待されます。 【日本語】https://www.tsukuba.ac.jp/journal/technology-materials/20211028140000.html 【English】https://www.tsukuba.ac.jp/en/research-news/20211028140000.html |
|
2021年8月17日 |
上殿明良教授(筑波大学数理物質系エネルギー物質科学センター(TREMS))が、応用物理学会優秀論文賞を受賞しました。 【業績】 https://www.tsukuba.ac.jp/journal/awards/20210803152046.html https://www.tsukuba.ac.jp/journal/awards/20210702143452.html |
|
2021年6月8日 |
山本洋平教授ら(筑波大学数理物質系エネルギー物質科学センター(TREMS))は、巨大な円偏光発光特性をもつ有機自己組織化マイクロ球体の作製に成功しました。球体1粒子の精密計測より、球体内部の分子集積構造について明らかにし、分子集合体からの角度異方的な円偏光発光を初めて実証しました。本研究成果は、次世代型の光技術に有用な円偏光発光マイクロ素子の開発や、キラルな光物質相互作用やトポロジカル欠陥などの学理研究への発展が期待されます。 【業績】有機マイクロ球体からの円偏光発光の角度異方性を実証 【日本語】https://www.tsukuba.ac.jp/journal/technology-materials/20210608140100.html 【English】https://www.tsukuba.ac.jp/en/research-news/20210608140100.html |
|
2021年3月5日 |
丸本一弘准教授(筑波大学数理物質系エネルギー物質科学研究センター(TREMS))は、電子スピン共鳴を活用し、従来の手法では困難だった原子層物質である遷移金属ダイカルコゲナイドの電子スピン状態を原子レベルで解明することに成功しました。独自に開発したトランジスタの構造を活用し、トランジスタ動作時に電子スピン共鳴を計測する、世界初開発の測定手法を用いた成果です。本手法で得られた原子レベルの情報を基にすることで、更なる高性能トランジスタの開発や磁性を活用した新たな半導体開発などが進むと期待されます。 【日本語】https://www.tsukuba.ac.jp/journal/technology-materials/20210305190000.html 【English】https://www.tsukuba.ac.jp/en/research-news/20210305190000.html |
|
2021年2月5日 |
中村潤児教授、武安光太郎助教(筑波大学数理物質系エネルギー物質科学センター(TREMS))は、燃料電池の白金代替触媒として期待されている窒素ドープカーボン触媒について、反応の初期過程および酸性環境下で活性が低下するメカニズムを均一な構造を持つモデル触媒を用いることによって明らかにしました。 【業績】窒素ドープカーボン触媒の反応メカニズムを解明 https://www.tsukuba.ac.jp/journal/technology-materials/20210108140000.html |
|
2021年1月12日 |
中村貴志 助教(筑波大学数理物質系エネルギー物質科学研究センター(TREMS))が、
公益社団法人・日本化学会第70回進歩賞を受賞しました。 |
|
2020年12月22日 |
丸本一弘准教授(筑波大学数理物質系エネルギー物質科学研究センター(TREMS))は、電子スピン共鳴を活用し、従来の手法では困難であったペロブスカイト太陽電池の劣化機構を分子レベルで解明することに成功しました。独自に開発した太陽電池の構造を活用し、電子スピン共鳴と太陽電池の性能を同時に計測する、世界初開発の測定手法を用いた成果です。この手法で得られた分子レベルの情報を基にすることで、低コスト、高効率かつ長寿命な太陽電池の製品開発が効率よく進むことが期待されます。 |
|
2020年12月15日 |
山本洋平教授(筑波大学数理物質系エネルギー物質科学センター(TREMS))と櫛田研究員が新しいゲル状電気化学トランジスタを開発。有機電気化学トランジスタ(OECT)は、従来の有機トランジスタの千倍以上の電流を流すことができますが、電流のオン/オフが切り替わる際の応答速度が非常に遅いという課題がありました。
山本教授、櫛田研究員は、有機半導体ナノファイバー中にイオン液体を取り込んだゼリー状材料「πイオンゲル」を電極上にのせるだけで機能する、新しい電気化学トランジスタ「PIGT」(π-ion gel transistor)を開発しました。20マイクロ秒以下という世界最高速の応答性と非常に大きな電気伝導性の両立し、フレキシブル電子デバイスへの応用が期待されます。 |
|
2020年12月8日 |
筑波大学数理物質系物理工学域・エネルギー物質科学研究センター(TREMS)の岩室憲幸教授が、ショットキーバリアダイオード(SBD)内蔵SiCトレンチMOSFETの実用化に向け、ショットキー金属をチタンからニッケルに替えることで、他の特性を犠牲にすることなく信頼性を大きく向上することができました。これにより、SBD内蔵SiCトレンMOSFETの実用化に大きな道筋をつけました。本研究は、産総研・富士電機(TPEC)との共同研究の成果である「トレンチ側壁にダイオードを内蔵したSWITCH-MOSFET(SBD-wall-integrated trench MOSFET)の検証」を研究され、NEパワーエレクトロニクスアワード2020の最優秀賞受賞を受賞されることとなりました。 |
|
2020年10月26日 |
桑原純平 准教授、神原貴樹 教授(筑波大学数理物質系物質工学域・エネルギー物質科学研究センター(TREMS))が、環境への負荷が少ない材料や合成法の開発の一つとして、藻類が作る炭化水素(オイル)に注目した研究を行いました。この藻類オイルや植物由来の精油成分など持続生産可能な資源と、石油の精製過程などで生じる余剰資源のイオウから、赤外光透過性とゴムのような弾力性を併せ持つ高分子材料を開発しました。この研究成果は、加工が容易で安価な赤外光透過材料の開発という、社会のニーズに応える端緒となることが期待されます。 |
|
2020年2月14日 |
近藤剛弘准教授(筑波大学数理物質系エネルギー物質科学センター)がTREMSのマテリアル分子設計部門の成果として、ホウ化水素シートに関する構造解析と電気伝導度に関する論文がChem誌に正式掲載されました。 |
|
2019年12月10日 |
近藤剛弘准教授(筑波大学数理物質系エネルギー物質科学センター)及び、物質・材料研究機構を中心とする共同研究グループは、ホウ素と水素のみからなる導電性を持つ新たなナノシート材料を開発しました。また高輝度光科学研究センターと共同で、ナノシートを構成する水素原子が特殊な配置を取っており、その構造が原因で分子が吸着することにより導電性が大きく変化することを明らかにし、Chemにオンライン掲載されました。この知見は、軽量かつフレキシブルで、導電性を制御できる本材料として、ウェアラブルな電子デバイスや新しいメカニズムのセンサーなどへの応用展開が期待できます。 |
|
2019年10月25日 |
近藤剛弘准教授(筑波大学数理物質系エネルギー物質科学センター)及び、東京工業大学 物質理工学院 材料系の河村玲哉修士課程2年、宮内雅浩教授、Nguyen Thanh Cuong(ニュエン タン クオン)研究員、岡田晋教授、高知工科大学の藤田武志教授、東京大学物性研究所の松田巌准教授らの共同研究グループは、ホウ素と水素の組成比が1:1のホウ化水素シートが室温・大気圧下において光照射のみで水素を放出できることを見出し、Nature Communications誌に掲載されました。 |
|
2019年9月13日 |
羽田真毅准教授(筑波大学数理物質系エネルギー物質科学研究センター) 及び、加藤隆史教授らの研究(東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻)が、液晶の中にあるアゾベンゼンの分子が、光を照射されると瞬時(100億分の1秒)に集団的に運動する現象を初めて観測することに成功し、Nature Communciationsに掲載されました。この知見は、光を用いた分子機能集合体(分子分子ロボットや人工組織など)への応用に大いに役立つと期待されます。 |
|
2019年7月16日 |
浙江大学一行来訪 ~TREMS施設見学・意見交換~ 【写真②】 |
|
2019年6月25日 |
筑波大学数理物質系(エネルギー物質科学研究センター) 全 家美博士研究員、近藤 剛弘准教授、中村 潤児教授らの実験グループ、および、国立大学法人大阪大学大学院工学研究科 Fahdzi Muttaqien(ファージ・ムタキン)特任助教(常勤)、濱田 幾太郎准教授、森川良忠教授らの理論計算グループは共同で、銅触媒表面での二酸化炭素の水素化反応が、二酸化炭素の分子振動励起によって駆動される反応であることを明らかにしました。 |
|
2019年5月31日 |
山本洋平 教授(マテリアル分子設計部門)が、第43回 レーザー学会奨励賞を受賞しました。 |
|
2019年5月26日 |
産業技術総合研究所 触媒化学融合研究センター 総括研究主幹 藤谷忠博 教授(基礎融合リサーチグループ)が公益社団法人 石油学会 2019年度 学会賞(学術的)を受賞しました。 |
|
2019年3月20日 |
中村潤児 教授(マテリアル分子設計部門)が、触媒学会 2018年度 学会賞(学術部門)を受賞しました。 |
|
2018年10月24日 |
筑波大学数理物質系の都甲薫准教授、末益崇教授、同大学院数理物質研究科の草野欽太(博士前期課程2年生)、および産業技術総合研究所の山本淳研究グループ長らの研究グループは、無機材料を用いた高性能フレキシブル熱電薄膜の開発に成功しました。 |
|
2018年8月10日 |
筑波大学数理物質系・西堀英治教授、笠井秀隆助教、数理物質科学研究科・佐々木友彰(博士後期課程3年)は、大型放射光施設SPring-8の高エネルギー放射光X線粉末回折により、アルミニウムの精密な電子分布を観測し、これまで知られていなかった電子分布の存在を確認しました。 |
|
2018年6月22日 |
筑波大学数理物質系・山本洋平教授、同大学院数理物質科学研究科・岡田大地(物性・分子工学専攻 博士後期課程3年)は、神奈川大学理学部・辻勇人教授、東京大学大学院理学研究科 中村栄一特任教授、産業技術総合研究所、ストラスブール大学との共同研究で、π共役系分子マイクロ結晶からの同時多色レーザー発振に成功しました。 |
|
2018年6月20日 |
筑波大学数理物質系 伊藤良一准教授は、同大学院数理物質研究科・胡凱龍(博士後期課程2年生)、大阪大学大学院基礎工学研究科 大戸達彦助教らと協力して、水の電気分解において、酸性条件下でも腐食しない卑金属電極を開発しました。 |
|
2018年3月30日 |
筑波大学数理物質系伊藤良一准教授は、大阪大学 大戸達彦助教、東北大学 阿尻雅文教授らと協力して、シリカナノ粒子を付着させたニッケルモリブデン卑金属多孔質合金の上にグラフェンを蒸着することで、ナノサイズの穴の空いた3次元構造を持つグラフェンで覆われた、酸性電解液中で長時間溶けずに水の電気分解で運用できる水素発生電極を、世界で初めて開発しました。 |
|
2018年2月21日 |
筑波大学数理物質系 山本洋平教授らの研究グループは、東京工業大学、京都大学、ハイデルベルク大学との共同研究で、π共役デンドリマーから形成する多孔性マイクロ結晶の作成に成功しました。 |
|
2018年2月13日 |
筑波大学 数理物質系 笠井秀隆助教らの研究グループは、公益財団法人高輝度光科学研究センターと共同で、原子のシートが積み重なった構造を有する層状物質TiS2(硫化チタン)内の電子の空間分布を、大型放射光施設SPring-8を用いて観測しました。 |
|
2018年1月11日 |
東京大学大学院理学系研究科の大越慎一教授と筑波大学数理物質系の所裕子准教授らの共同研究グループは、固体物質において相転移現象が発現するか否かを、コンピュータ計算により予測可能であることを明らかにしました。 |
|
2018年1月5日 |
神原貴樹教授、物質・材料研究機構 安田剛主幹研究員らの共同研究グループは、有機電子光デバイス用高分子半導体を合成するための新しい合成技術の開発に成功しました。 |
|
2017年12月9日 |
守友浩教授の研究グループは、コバルトプルシャンブルー類似体を正極と負極に配置したイオン電池型熱発電セルを作成し、28℃と50℃の温度サイクルで熱発電を実現しました。 |
|
2017年12月5日 |
都甲薫准教授、末益崇教授らの研究グループは、ガラス上に合成した半導体薄膜として最高の正孔移動度を持つゲルマニウム(Ge)薄膜の開発に成功しました。 |
|
2017年10月18日 |
柳原英人教授らの研究グループは、(株)デンソー、東北大学と共同で実施するNEDOプロジェクトにおいて、鉄とニッケルが原子レベルで規則配列したFeNi超格子磁石材料の高純度合成に世界で初めて成功しました。 |